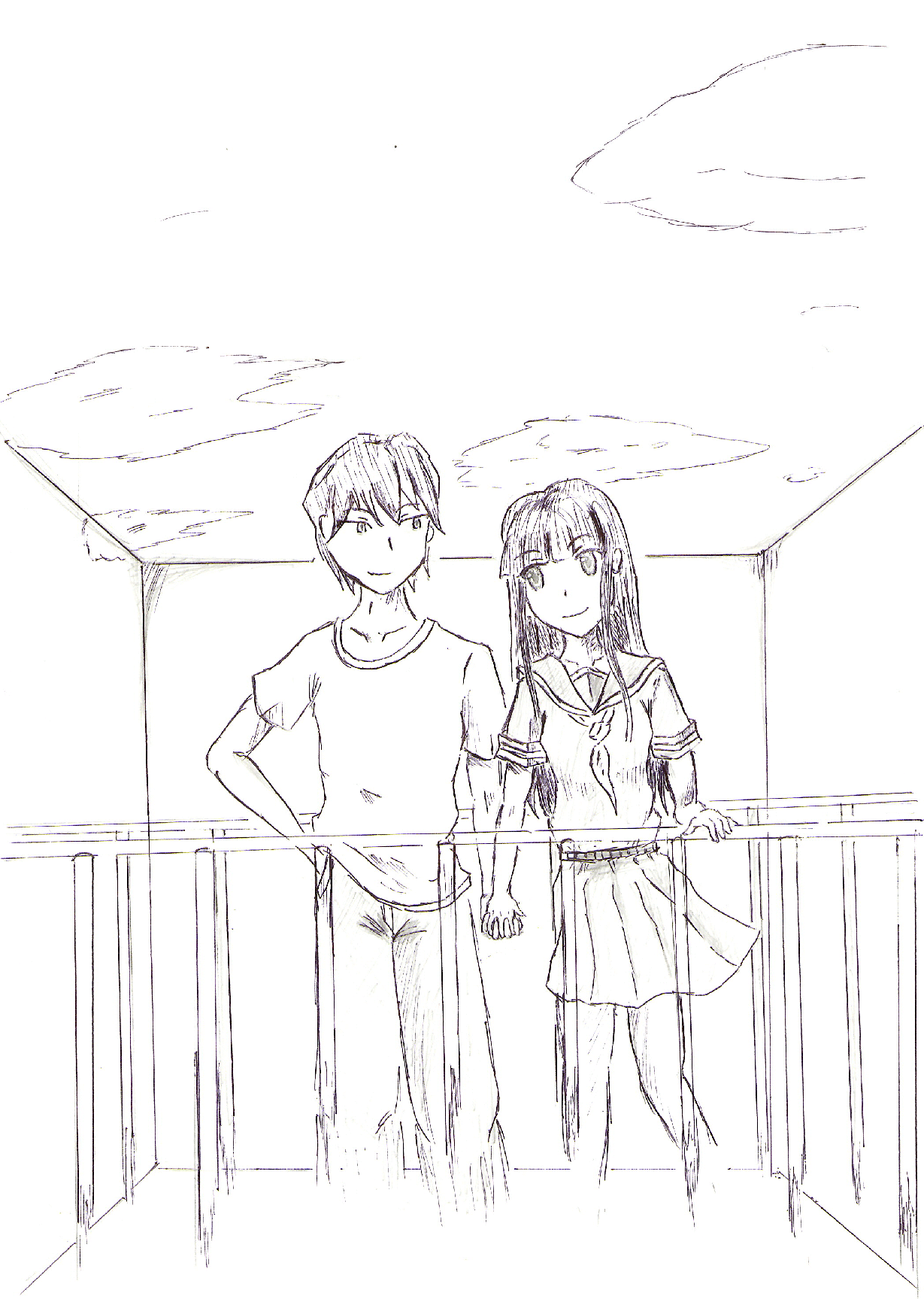【プロローグ】
新生活。
大学に合格した。
もう何も俺を阻むものはない。さぁ大学で明るく楽しいキャンパスライフを送ろう。そう考えていた俺の前に立ちはだかった引越しという名前のそいつは、俺の盲点をつくかのように意外にも面倒なものだった。
一人暮らしに憧れる高校を卒業したばかりの生まれてこの方親元を離れたことのない糞ガキ。そいつがまぁ一人で見慣れぬ街に住むところを決めだの家具を買いだのできるわけもなく。本人が自覚している以上に親はそのことを承知で、まぁつまりは住むところから通学方法まで親が決めてくれてそのど真ん中に最後の仕上げとばかりに俺はぽいと放り込まれたというわけだ。まったく死ぬまでこのわが子のために苦労や手間を惜しまぬ両親には足を向けて寝られない。
ともかくもこうして俺は住むところも通う大学も決まり、晴れて大学生としての輝くべき栄光の一歩を踏み出したわけだ。
さて、こんな話がどうしたというのか。
どの学生も大概は通る経験じゃないか。
そんな意見はごもっとも。
じゃあこんな話はどうだろう。
ちょっと同じような体験をした連中ってのは聞いたことがないのだが、まぁ聞いてみてくれよ。
というのも実は俺が敬意払うべき父上母上の用意した国営の借家はとんでもない代物だったんだ。
言い遅れた。
俺の名前は相沢真。
この物語の主人公だ。
【一章】
六畳間の真ん中に堂々と布団を敷いて、その上にごろんと寝転がる。友達がいないのに加え親に頼んだテレビがまだ来ないという二重の悲劇に見舞われた俺は、暇という名の荒波に見事に押し流されていた。
そしてそんな波に乗ってきたのだろう。つい先日までいた狭い実家の風景がふっと頭の中に湧いて出る。
自室に居ても階下のリビングから聞こえてくる両親の会話。
隣の妹の部屋から夜な夜な漏れ出るうしししという謎めいた声。
エロ本を熟読していると突然侵入してくる愛すべき、されど憎さ余って可愛さゼロの愛称ババア。
そんな情景たちは、この部屋の静けさと一人暮らしの寂しさとをより一層膨らませてから、満足したかのようにぽっと消えていきやがった。
こんな糞ガキにもホームシックなんてもんが来ようとはな。笑わせてくれる。
一人暮らしで伸び伸び出来るはずだったのになぜだろう、ほんの少し息苦しさを感じていた。
あれは、そんな時だった。
「やぁ少年」
突然、俺しかいないはずのこの部屋に、女の子の声が……した?
起き上がって声のした方を振り向くと、そこには真っ白な壁。
隣の人(確か女子大生だったはず)の声か?何だ?一体何の声だ?隣人の自慰行為か?はたまた隣人による自慰行為か?
そんなエロ直結の思考の元、隣の部屋との境界である白壁に右耳を当て、必至に音を拾おうと壁に体を寄せる。
だがアドバルーン大に膨らんだ下品極まりない期待とは裏腹に、それ以降右耳からは一切の音が入ってこない。
空耳かふざけんなくそっ、と行き場のない憤りを抱えながら壁から耳を離すと
「おーい、こっちじゃ」
今度は部屋の反対側の壁から、またしても女の子の声が聞こえてきた。
何だ何だ、今度はこっちの隣人(確か人妻だったはず)が催しちゃったのか?と左耳を当てて待機するが、またもや何も聞こえやしない。くそがっ。
耳を引きはがして布団の上に座り、憤りの冷めるや数分。冷静になってから、俺は不意に大事なことを思い出した。
俺はアパートの二階、角部屋に住んでいる。
最初に右耳を当てた方の壁から声が漏れ出るのは良しとしよう。
だが、次に左耳を当てたこっちの壁からは、声が漏れ出てくるはずがない。人妻はよくよく記憶をほじくり返せば、横でなくこの真上の部屋だった。
気のせい、で片づけるのはあまりにも安易であろう。なぜなら、残念ながらあの壁からの声は今も脳にぺっとりとこびり付いているからだ。
そしてふいに俺は思い出した。
最初に聞こえた声と二回目に聞こえた声、今思えば、だいぶ似ていたような気がしないだろうか?両方とも、少し幼さが滲み出た、高めの声。脳内にこびり付いた二つの声を同時再生して比べてみる。ああ、やっぱりそうだ。同じ声だ。同じ人の声だ。
さて、ともするとこれは一体どういうことだろう?
声のしないはずの壁から声。左右から同じ人の声。
つまり……一体どういうことだ?
考えろ。壁からの声。一致した声。元からすかすかの頭を雑巾のように固く振り絞り、捻り出した結論はこんなものだった。
「…………まあそういうこともあるだろ」
そう。こういうこともあるだろう。面倒だったので深く考えないことに。
声について闇に抹消してしまおうと思いぐるぐる布団に包まって寝ようとした。すると
「阿呆か貴様。そういうこともあるわけないじゃろ!」
「ふぁっ?!」
ほんのついさっき二回も響いた声と同じ、少女の声。しかし今度の声は何を隠そう、天井から降ってきたのだ。
慌てふためく俺に更なる仕打ちが襲いかかる。
「そんなすぐにびくびくしおるから肝っ玉も下の玉も小さいんじゃ、少年」
今度は俺が座っている布団の下あたりから声がした。
……なんだよこれ。
「お〜い少年、落ち着いたか?お〜い」
唖然としていると、今度は斜め上の方向から声。どういうことだ…。ついに俺、頭がおかしくなっちゃったのか?と頭を抱えて布団の上をごろごろ転がっていると
「いいから落ち着いて舞の話を聞け」
また声がした。
果たしてこの状況で落ち着いていられる人間がどれだけいるだろうかと思いつつ、一つまみの勇気と好奇心から俺は虚空に聞き返してみる。
「話って何だよ。あと舞って……?」
「ああ、やっと冷静になったか。じゃあまず最初に言わせてもらうとな、私は………、この部屋なんじゃよ。そんで舞ってのが私の名前じゃ。桜川舞。可愛らしい名前じゃろう?」
「は?」
「だから桜川舞じゃ」
「いやそっちじゃねえよ。部屋って……?」
「だから舞は部屋なのじゃ」
部屋なのじゃ……部屋なのじゃ?
何度か脳内で繰り返してみるが、上手く意味を咀嚼出来ない。混乱している頭に横から、また声が。
「というわけで、これからよろしくな」
「待て待て待て、どういうことだ?部屋?」
「だからそう言っておろうに」
さも当然といった声が床から跳んでくる。
「いやいやいや、俺はそんなの信じねえぞ」
「まあ普通はそうじゃろうな。じゃが」
声がした。天井から。
「舞が部屋だとすれば」
右側の壁から。
「声がいろんな所から」
床から。
「聞こえてくるというこの現象も」
押入れから。
「納得出来るじゃろ?」
エアコンから。
部屋の至るところから断続的に、舞というらしい女の子の声がした。
「ま、まあ確かにそうだが………いや………うー………?」
さてどうしたものか。突然聞こえ出した声は自身を『部屋』だという始末。しかも地味に説得力がある……あるか?
「これでも納得しないようなら仕方ない。三百六十度、四方八方から世を恨み妬みしながら血の涙を流して死んだ娼婦の如き声色で『般若心経』を唱え続けるしかあるまいな………一晩中」
「やめろおおおおお」
どんな悪夢を見せるつもりだ。
「じゃあ舞が部屋じゃと認めるか?少年よ」
「………………」
真正面の壁からストレートに飛んできたその問いに、散々躊躇しつつも最終的には根負けする形で俺は首を縦に振った。振ってしまった。
「じゃあこれからよろしくな!少年」
股間の下から俺の股についてる何かを振動させるぐらいに大きな声が響いた。
決してこの声の主が部屋であると認めたわけではない。面倒だから首肯しただけだ。と一体なにに対してか分からない言い訳を自身にいい聞かす。
そうして俺の、『部屋』たる舞と過ごす日々が始まった。始まってしまった。
え、俺のプライバシーどうなんの?
【二章】
舞が自身を部屋だと言って俺を困惑させた日から数日、数週と経つにつれ、部屋の至る場所から声のする生活にも徐々に慣れていった。
夕飯を調理している最中、突然「うまそうなもん作っとるな少年。半分くれ」と舞の声がしてビビってフライパンを引っくり返し、野菜炒めを全滅させた。
熱で寝込んでいるときには「よし、舞が治してやろう」と声だけでナースごっこを始めて、病状を悪化させていった。
風呂でシャワーを浴びている時、突然「背中、流してやろうか少年?」と妖艶な声で来ては、俺のチョコバナナ(隠語)が膨張するのをクククと笑っていた。
布団に入って目を閉じて寝ようとしていると、「どれ、添い寝してやろう」と眠気が極限値に達するまで話し続けた。
部屋の声がするというからには、これからの俺の生活は一体全体どうなってしまうんだと不安に思ったこともあった。が、大したことはない。結局はうるさい奴が寄生虫のように住みついているだけなのだ。
今だってそうだ。
さあ寝るかと明かりを消そうとしたところに「暇だ、少年」ときた、天井からの声。
「俺は寝るぞ」
「まあ待て。少年、今日は耐久勃起ゲームをしよう」
「…………なんだよそれ」
聞き返した直後に聞き返したことを後悔した。まずゲーム名からしてろくでもないことが伺える。
「その名の通り。勃起を耐久するという、少年がいかに変態かを実証するためのゲームじゃ。十分間、舞のエロボイスに少年が耐えきれれば少年の勝ち。勃起したら少年の負けじゃ」
「紛れもないクソゲーじゃねえか」
「さあて、どんな声で籠絡してやろうかの……ぐっへっへっへ」
「うわあ…………」
その舞の下品な笑い声たるや、中年エロオヤジにも引けを取らない不気味さがある。
「よし、早速始めるとするかの」
「おいおいおいまだ俺はやると言ってな」
「ん?じゃあ自身の変態っぷりを認めるか?まあ仕方ない、『童貞』じゃもんな」
「おい、今なんて……?」
「『童貞』と言ったのじゃ」
「ノーバディーコールズミー、ドゥーティー!!!ファーーーーー」
『童貞』というその響きが俺の体中に流れる血を沸騰させる。
その昔、チキンと言われてカッとなる主人公がいたが、俺は彼と同じ血が流れているのかもしれない。俺が映画出演出来ないのは『チキン』と『童貞』の間を遮る壁がデカすぎただけだ。
「いいだろう、その勝負乗ってやる」
「ふっ、良い目をしとる。相手にとって不足なしじゃな。そこのタイマーを取るがいい」
「おし。……って、タイマーなんてないぞ」
「は?少年の枕元のやつじゃよ」
「もしかしてこれか?」
枕元のスマホを手に取る。他に枕元に置いてあるのはパソコンと飲みかけのジュース缶だけだったから、おそらく舞の言うタイマーとはスマホのことを指していたのだろう。
「そうじゃよ全く、時間稼ぎか?」
「いやいや確かにスマホにはタイマー機能もあるが。これはタイマーじゃねえよ」
「スマホ…………?何じゃそいつは?」
「えっ、舞まさかお前スマホを知らねえのか?」
「…………悪かったな。時代遅れで」
舞は馬鹿にされているように感じたのだろうか、ムスッと尖った声が帰ってきた。
しかし本当にスマホを知らないのか…。
何か引っかかるところもあったが、これ以上舞の機嫌を悪くするのは御免だ。
舞は機嫌を損ねると俺に『無言の圧力』をかけてくる。聞こえているはずなのに俺の言葉に一切返事をしない。あの状況は、急に低酸素室に連れ込まれたような息苦しさと象に踏まれるような重いプレッシャーが持続するので、本当に二度と味わいたくない。
俺は普段より明るい声を出して悪い空気を一気に押し流した。
「よし、じゃあ勃起ゲーム、するか!」
セリフの選択を盛大に間違えたことに気付いたのは言ってからのことだ。
しかしそのおかげで舞も何とか機嫌を直したのか、天井から声が返ってきた。
「勃起ゲームじゃない、耐久勃起ゲームじゃ。少年の竿を数秒にして起立させてやるわ!」
そうしてゲームを再開する。
結局、勃起ゲームは舞の圧勝で終わった。記録、四十五秒。情けない限り。
そんな風にしてなんだかんだで舞とは確実に打ち解けていった、と思う。少なくとも俺はそう思っている。
だからというわけでもないが、ある時俺は舞に少し踏み入ったことを聞いてみた。何故聞いたのかといえばただの蜃気楼のような気まぐれにすぎなかったのだけど。
「なあ、俺より前にこの部屋って住人はいたのか?」
「ん?いきなりどうしてそんなこと聞くか少年」
「いや、舞ってちょいちょい現代のもの知らないだろ、スマホとかPSVitaとか。それって、相当長い間一人だったってことなんじゃないか?」
「あー、確かに。前のやつが出てったのはいつじゃろうな、数えておらんから分からんがもう十年近く前かもしれん。舞が部屋になったのなんてもう二、三十年前な気がするしな」
十年近く……まじかよ。ってあれ?もっと凄まじい事をさらっと聞いた気がする。
舞が部屋になってから二、三十年。
部屋になってから。
「部屋になってから!?お前、昔は部屋じゃなかったのか……?」
「あ、言っておらんかったか?舞は昔は普通に可愛い女の子じゃったぞ」
「はあああ?ほんとかよ?」
「ああ」
驚愕の新事実。舞は人間だった。そもそも部屋がしゃべること自体が驚愕沙汰ではあるが。
「何がどうなって部屋になった?」
「んー、それを説明するのはちと無理じゃな」
これ以上は踏み込んではいけないラインなのか。
「人間に戻りたいとは思わないのか」
しかし俺は不覚にも思わず踏み込んでしまった。しかし舞にとって、それは大したことではなかったらしくあっさりと答えた。
「まあそう思うこともある。しかし部屋になるのは舞が望んだことなんじゃ」
「……ほう?」
望んで部屋になった?何故だ?例えば、元々の舞が不治の病を患ってて部屋になることで生き永らえたとか?まさか。
分からない。
「そんなことより、少年、テレビつけてくれ。もうすぐアニメの時間じゃ」
「ああ」
この時脳内に渦巻いていたもやもやは、テレビの中をパンツ姿で飛び回る少女にかき消されてしまった。
数週間後、俺は休日をほとんど家で過ごすようになった。
更に数週間経ち、大学に行く日がめっきり減って、平日もほとんどの時間を部屋で過ごすようになった。
夢に見ていたキャンパスライフというやつは、外からはキラキラと多くの人間を魅了するダイヤのように光輝いて見えても、いざ中に入ってみるとそれは空を覆い尽くす雨雲のように、どんより灰色に濁っていた。
友人が出来なかった。入学式早々、友達グループがどんどん形成されていく中、奥手の俺はただぼんやりとその様子を眺めて、結果気づいたら一人取り残されていた。
授業についていけない。自主性に任せる大学の教育方針は、齢十五にして手に入れた勉学への志を大学受験が終わってから一気に失った俺を易々と叩き落した。
しかし俺はこの時点ですでにこう思っていた。
何の意味もない。大学なんか。
今日は一年必修の中国語があるにも関わらず、朝から家にひきこもっていた。
「おい少年、大学には行かなくてよいのか……?進級のためにと水曜だけは大学に行っておったじゃろう?」
不安げな舞の声が耳に入ってくる。
「ああ、もういい」
「どうしてじゃ」
「俺、ひきこもりになるよ」
「…………なんじゃと?」
数ヶ月聞き続けたからこそ、その舞の声がほんの少し曇ったのが分かった。
俺は続けた。今考えると少しヤケになってたとも思う。でもその時は本気だった。
「ひきこもりってさ、最高じゃね?大学に行かなくていい。会社に行かなくていい。いくら遊んだって問題ない。素晴らしいと思わねえか?」
「……舞はそうは思わんぞ」
「何でだ?」
「何でって、当たり前じゃろ。じゃあどうするんじゃ?食い繋いでいくには?親に頼るのか?それこそ最低じゃぞ。先のこと考えないのか?」
「だからさ、そういうこと考えなくて良いんだって。それがひきこもりなんだって」
「それでも、そうはいかんじゃろ……」
「それに、この国ってさ、ひきこもりが全然いないんだろ?」
そう、この国にはひきこもりがいない。
「………政府の機密の『政策』だかのことかの?」
「ああ。教育課程で無意識にひきこもりへの嫌悪感を埋えつけられる、って噂だ。だから、そんなもんを覆して俺がひきこもりになってやる。かっこよくないか?国唯一のひきこもりってさ」
「全くかっこ良くなどない。阿呆か。とにかく駄目じゃ」
「何でだよ。何でそんな反対するんだよ?舞だってずっとひきこもってるようなもんだろ。それに、ひきこもれば、もっと舞と居られる時間が増えるだろ!」
止める間もなく、俺の本音は飛び出てしまった。
狭い六畳間に沈黙が訪れる。
先に口を開いたのは、舞だった。
「それでも、駄目じゃ」
「っーーー、理由を言えよ。駄目だ駄目だじゃ分かんねえよ。ひきこもりのどこがそんなに舞にとって気に食わねえんだよ。俺と居るのが嫌ならそう言えよ」
「違う!そうではない。じゃが、ひきこもりというのは少年の言うように甘ったるいものではないんじゃ。永遠の闇、孤独、希望の欠片もない世界、少年はそんなものに耐えられるのか?」
今までに聞いたこともないような、ドスのきいた低い声に思わず怖気づいてしまう。
だが俺はそんな舞の言葉を大げさだ、と思った。ひきこもりという単語を何か別の単語と間違えて覚えてるのではないか、と思うほどに。闇?孤独?希望のない世界?馬鹿な。ひきこもりは希望で満ちている。再度繰り返すが俺はこの時は本気でそう思っていたんだ。
「すまんな少年、怖い声を出してしまって。少し頭が冷えるまで引っ込むことにする……」
「あ、ああ……」
今度は打って変わって落ち込んだ声。どうしたんだろう。今日の舞は、明らかに様子がおかしい。ひきこもりってのがそんなに気に障る単語だったのか…?それにしても反応が過剰な気がする。
分からない。
分からない。
【三章】
「少年少年、部屋の隅にきのこが生えておるぞ!今晩の夕食にどうじゃ。きっと舞の成分が染み出してるじゃろう」
「丁重にお断りする」
舞の様子がおかしかったのは、夕方にはすっかり元に戻っていた。
昼のような惨事をわざわざ再現させることもあるまいと思い、俺のひきこもりの件についての話題は避けているが。
そうして他愛のない話を続ける。
「今晩のおかずは何じゃ?」
「んー、鮭の切り身かな」
「他にはないのか?」
「ああ、もう冷蔵庫には何も残ってねえ」
「そうじゃな……………………。何たって少年は、ひきこもりだからな」
それは唐突な一言だった。
何だ?
突然舞が持ち出した、ひきこもりという単語。
「え?」
「少年は、ひきこもりじゃからな」
念押すようなその言葉と同時。俺は部屋の中心辺りに、人型の、幽霊の様な、黒い影が出来上がるのを見た。
「成功じゃ。やはり改心しなかったようじゃの」
少し残念そうに舞の声が聴こえた。その人影から。
「成功……?」
「ああ。おっと、そうじゃ少年、以前舞が何で部屋になったか聞いたことがあったな?少しだけ説明しよう」
「…………おう」
部屋の中心の黒い影が、少しずつ色を帯びていく。
気のせいか、体が金縛りに遭ったように動けない。
「舞が部屋になったのは政府の『政策』が絡んでおって、舞は昔ひきこもりじゃった。言えるのはそれだけじゃ」
「おい、説明になってないぞ」
「まあ少年はこれから理解するじゃろ」
これから?政策?部屋?いろんなものがごちゃっと複雑に絡み合っていて、うまく理解できない。
影だったものは、さらに色を集めていって、今は人にモザイクをかけたようなものになっている。
影が色を纏うにつれ、俺は動けなくなっていた。固定されていくような、逆に固定されてないような、よくわからない感覚がする。視点がぐるぐる回る。
「ほら、舞の影じゃ。だんだん濃くなっているのに気づいておるか?舞は出て行くぞ。これからは少年が舞の代わりに部屋となるのじゃ。ヒキコモリたかった少年には望み通りのことじゃろ?」
影だったものは今や完全に普通の女の子へと変化していた。黒髪の、セーラー服を着た、しかしそれが似合わぬほど小さな女の子。この子が……舞なのか……?
じっくり見ようとするのだが、視界がぶれる。焦点が合わない。動けない。視点がおかしい。上からの視点。横からの視点。下からの視点ではスカートの中が見えた。待て待てそんな場合じゃない。
「おい待て、どういうことだよ?意味わかんねえよ、舞が人間に戻って、そしたら俺が部屋になる?説明してくれ」
「は、説明?だから言ったじゃろ?少年はこれから部屋になるのじゃ」
「なんだと……!?」
「うむ、久しぶりに空気を吸う感覚、たまらんな」
そういって舞は動くようになった新しい体で深呼吸したり手足を伸ばしたりした後、こう言った。
「じゃあのwww」
そして舞は、部屋から出て行った。
そして俺は部屋になった。
なんだこれ。
【四章】
え、ちょっと待てよ。
冗談だろ……。だってほら。違うじゃん。俺がこんな。だって。え?これで終わりか?俺は舞に見捨てられたってことか?頭が麻痺したみたいに動かない。舞の最後に残したセリフが頭をぐるぐるまわるけどその意味がわからない。ちょっと待て。状況を整理しよう。確かに俺はひきこもっちゃってもいいなと思ったさ。でもそれは一人でなんかじゃない。舞がいて、俺に話しかけてくれる、あの部屋にひきこもりたかったんだ。こんな俺自身が部屋で、でも舞がいない部屋なんて本末転倒。出来損ないもいいとこだ。いやだ。こんなの俺が望んだことじゃない。これは、これでは……あぁそうか。これが本当にひきこもるってこと。俺がそう呼んでいたあの部屋は本当のひきこもりなんかではない。じゃあ今俺は本当にひきこもってしまったのか。一人で。それはとてもさみしくて。死ぬほどツラくて。あぁ死んでしまったみたいだ。静かな部屋。静かな部屋。それはきっと俺が来る以前の舞の部屋。
ぶくぶくぶくぶくぶく
俺は溺れる。
静寂に。寂寥に。
小さな夢を何度も見る。
舞がいる夢だ。
それ以上覚えていない。
なのにそれだけで泣いてしまう、何度も何度も。覚めて。覚めたくなくて。俺は溺れる。
未来のない俺は過去を何度も。息の仕方を忘れるほどに。飲み干す。
あぁでもわかった。
あいつの気持ちが。
どうしてひきこもったかって?
こうなるのが怖かったからだろ?
一人になるのが怖いから最初から一人でいよう。
そうなんだろう?舞。
電話が何度も鳴って。切れた。
ある日母親が俺の中に来た。入居の日に俺が渡した合鍵を片手に不安に押しつぶされそうな顔をしながら、真?いないの?そう声を上げて探し、いないと知ると出て行った。
次の日も来た。泣きそうな顔で俺の中のあちこちを探しまわる。引き出しを探り、本棚をぶちまけ、カバンをひっくり返し。財布と部屋の鍵を見つけて、それを見つめたまま動かなくなった。日が暮れて部屋が真っ暗になっても動かず、晩遅くに父親がやってきた。電気を付けて、母親にまだそうと決まったわけじゃないと元気づけ、二人して部屋を探しまわり、肩を落として帰っていった。
次の日には警察が来た。
手には母親の持っていた合鍵。
両親に比べて大した探し方もせず帰っていった。
更に数日後。母親が葬式でも済ませてきたみたいな。いや済ませてきたに違いない。真っ赤に泣きはらした目とぐちゃぐちゃの顔で俺の荷物や殆ど使われなかった家具を一つずつ処分していく。本当に一つずつだ。本の一冊からテレビのリモコンに至るまでひとつずつ丁寧に残すもの、捨てるもの、譲るもの。分けて行った。時々倒れるように眠り、夜には仕事から帰った父親が怒ったようなやりきれない顔でそれを手伝った。何日もろくに寝ないで。それでも終わりは来る。突然に。すべての荷物が片付いてしまった。何が起こったのか両親はしばらく理解できなかったようで、小一時間ほどたってようやく自分らがもうダンボールに息子の遺品を詰める必要がないことを悟った。静かに泣いた。やがて立ち上がり。出て行く。ふと振り返って。さようならとつぶやく。
俺はとうとう最後まで一言も発することができず、誰も居ない空の部屋に向かってようやっと一言出せた。その言葉だけはどうしても教えられない。悪いな。
また空虚な日々が過ぎる。いつまでも。そう思っていた。しかしその予想はすぐに覆される。
【五章】
「説明に参りました」
男がいた。
俺の目の前に。いや俺の中に。
「政府指定財団生物不動産管理協会のカタガミと申します」
どうそ宜しくお願いします。そう言いながら頭を下げる。文字通りどこから見ても(下から見ても)完璧だった。一部の隙もない。赤いネクタイのスーツ姿の頭に白い物の交じる男。豪邸にいる万能執事を絵に描いたようと言えば伝わるか?だけど一点だけ欠点を上げるとしたら。
「インターホンを鳴らす必要は感じられなかったので」厭な笑い方をしやがることだ。「鳴らさずに上がり込ませて頂きました」くにゃっと嘲るような媚びるような笑い方をしながらそいつはこの部屋の鍵らしきものを宝石でも見せつけるかのように持ち上げる。
その男はこちらが黙っていることをまったく意に介せずに自らの宣言通り、説明を始めやがった。
「もうすでに桜川様にご説明をうけてらっしゃいますでしょうか?桜川舞様です。何もおっしゃらないということはされていらっしゃらないということでよろしいでしょうか。いえ、もちろん結構です。それを説明するために私がこのように派遣されて参りましたのですから。とは言え『聴こえた』限りで相沢様が確実にご存知なことは省かせて頂きますね。私の労力云々というより貴方様の退屈を慮ってのことですのでご容赦を」
「おい」俺はここで初めて声を出した。「『聴こえた』ってどういうことだ?」
「あぁ相沢様、やっと口を利いてくださいましたね。万が一にも聞いていただけなかった場合は私が何度でもこちらに参上して説明させていただく手筈となってましたので」
「んなことはどうでもいい」それより「『聴こえた』ってなんだ?」
「……」
男は笑ったまま。黙る。俺はその笑顔に腹が立ち、対抗して物音一つ発さなかった。部屋と人のにらみ合いが続いた。先に折れたのはヤツのほうだった。
「やはり部屋との我慢比べには勝てないものですね」苦笑しながらご丁寧に頭まで掻いて絵に描いたような困ったなという表情。「少しだけ自分は忍耐強い方だと自負していたのですがこれは認識を改めざるを得ませんね。いやはや参りました」肩をすくめる。
「ごまかすなよ」
思ったより低い声が出た。
「ごまかすつもりなんて毛頭ございません」ダウト。「よろしい、お答え致しましょう。盗聴です」
「は?」
「ですから盗聴でございます。失礼は承知の上で貴方様のお部屋には盗聴器をしこませていただいておりました」
「………なんでだよ」
「それも今から説明いたしますので、しばしお時間いただけますか?」
「早くしろ」
「はい、と申しましても。現状この通り部屋となられた相沢様には特に込み入った説明は必要ないかとも思われます」くにゃりと笑う。「まずこの部屋について。この部屋。つまり人柱式居住空間定位装置は俗に『システム』と呼ばれております」
「『システム』?」
「そのとおりでございます。この『システム』は我が協会が約二十五年前に開発いたしまして、現政府に提供。翌年には国民に明かされないまま秘密裏に使用され、今に至ります。具体的な使用方法を大雑把に申し上げますと、まず人間を用意する。このシステムは完全にコントロールを声に頼っておりますので、この人間が人柱となりうる人間。つまりひきこもりであることを別の人間が宣言する。その結果システムはこの宣言の真偽を判定し、真であると判断されれば人柱として用意された人間が『部屋そのもの』となります」
「……」
あまりに予想の範疇を大きく凱旋する話に俺の口はしばらくまともな言葉を発せなかった。
「つまり……いや、そもそもなぜ政府はそんなものを秘密裏に使っているんだ。目的は?」
「ひきこもりの抹消でございます」
「……なるほど」
「抹消というのはそのままの意味です。見たでしょう?自分の存在が行方不明という形で消されていくのを」
その無神経極まりない言葉に俺は歯があれば噛み砕いてたであろうほどの憤りを感じた。
「そして桜川舞様が代わりに部屋の人柱としての立場から解放される。すでに引きこもる意思をなくした彼女が」
「……え?」
「彼女は二十五年前の最初の人柱です。ご存じなかったのですか。当時の政府は増加する引きこもって社会に貢献しない若者を減らすことに執心しておりました。我が協会の開発品を採用し、人柱として数十名のひきこもりの若者を募集しました。集まったのは明日にも明後日にも望みのない、行き詰まるようにひきこもっていて、されどその状況が最悪のものであることを自覚していらっしゃった人々です。その中に桜川舞様が含まれていました。彼女らにも今貴方にさせていただいているものと同じ説明をしました。つまりこういう内容です。貴方達には部屋そのものとなっていただきます。声のみが出せる状態で貴方達の中へとやってくる居住者をひきこもらないように導いてください。ひきこもっていた人間が他人をひきこもらないように説得する。これは一見現実味のない話ですが、実際にはこれほど効率のいい方法もないのです。元ひきこもりの人柱は誰よりもひきこもりに精通しているため、うまく使いさえすれば予想外の結果を引き出すという理屈ですね。実際に彼らはこの国からひきこもりを消しさりました。これは彼らの尽力のお陰です。しかしもちろんそれだけではない。最後に我々は彼らが解放される二つの条件を付け加えたのです。一つ、貴方達の中へいらっしゃる居住者を五人更生した場合。もう一つ、貴方達の中へいらっしゃる居住者が貴方達の『尽力にも関わらず』ひきこもりになってしまった場合。このどちらかの条件を満たした場合、貴方達は解放される。そう説明いたしました」
「その代わりに新たな人柱が部屋となる、というわけか」
「後者の場合、そのとおりでございます。さすが理解が早い。であればこれも想像つくかと思われますが、人柱達は故意に居住者をひきこもりに仕立てようとするやも知れません。それを防ぐための盗聴器です。そしてこれら全体がこの国からひきこもりを抹消した『政策』です。いかがです。素晴らしいでしょう。常にひきこもりと呼ばれる人種はこの国には存在し得ないのです。無駄な人材は部屋としてストックしてしまえばいい。その人間が改心して社会復帰が果たせるようになるまで国営住宅という名の倉庫に放り込んでおけばいいのです。『政策』によって、ひきこもりを防ぐ役割を務めさせられながら」
「……確かにそれは正しいことかもしれないな。ひきこもりが自然といなくなるんだし、別に殺すわけでもない」
「その通りでございます。もちろん開放された人間、今回の場合桜川舞様ですが、彼女には戸籍を与え生活空間、金銭、補助者、労働環境、教育機関、その他細かいところまで行き届いた補償を行っております。二十五年前の人間が現代でまっとうに生きていけるように」
「それはもう痒いところまで手の届く充実っぷりだな。だけどさ、ひきこもりってそこまでして無くさないといけないものなのか?そもそもひきこもりの何がいけないんだ?」
「人間は一人では生きていけません。個人は他人とのつながりを通じて生きるのに必要な様々な物を獲得します。ひきこもるとはその関係を破壊するということです。それはその人間のみの関係ではなく他人の関係の和をも乱すものです」
「だから抹消しなくてはならない?」
「何かご不満でも?」
相変わらず厭な笑い方をする。それはきっとわかってやがるからだ。ここで俺が何を言ってもそれは自業自得で部屋になってしまった、国からしたら犯罪者級のひきこもり人間の独り善がりな負け犬の遠吠えってやつにしかならないと。それでも構わず俺は言った。
「大いに不満だな」
「ほう」
これはおもしろいとばかりにヤツは目を細めた。
「他人とつながる。それは大事だろう。それを拒絶することは自分だけの問題じゃない。そのとおりだ。だけど俺は納得行かない。つまり臭いものに蓋をするってやり方だろ、お前らのそれって。ひきこもってた人間の問題をその『政策』ってやつに丸投げしたんだろ。それって何か矛盾してないか?」
「矛盾?何がでしょうか。馬鹿馬鹿しい」
男ははっきりとこの時嘲りを笑みに混ぜた。
「そんなものはない。むしろ矛盾だらけなのは貴方達の方ですよ。ひきこもるくらいなら死ねばいいんです。死ねないというから仮死状態としての部屋になれといえばまた貴方のように根拠無く感情論で批判する人間が出てくる。だから無視されるんです。だからひきこもらざるを得なくなるんです。そんな貴方達を我々国家は認めない」
「ならば舞達も貴様らのその処置を認めないぞ!!!」
幼いのに口調が古臭い、矛盾だらけの懐かしい声が聴こえたこの時、俺は驚きのあまり声が裏返っちまった。
「ま、舞?」
その声は玄関から聴こえた。カタガミがゆっくりと振り返る。
「これはこれは桜川様、お久しぶりです。二十五年ぶりでしょうか。本日はどういったご用件でいらっしゃったので?」
「久しいのう、カタガミ。あの頃は駆け出しだった貴様も出世したか?しかし偉くなると耳も遠くなるようじゃの。言ったろうが、舞達は貴様ら政府のやり方を認めない」そしていい顔で不敵に笑いやがった。「反逆じゃ」
「ほう」
「貴様らの主張することはまぁ間違っていないじゃろう。舞達のようにひきこもる人間が正しいとも言えないな。じゃが貴様らの取った方法は上から下まで間違っておる」
「言いますね、何故そうまでおっしゃられるのですか?」
「貴様らはひきこもる人間が他者とつながらないことを否定する。しかし他者とはなんじゃ?自分以外か?ならば床を叩いて親に食事を要求する輩はひきこもりではないな。では家族以外か?しかし家族の誰かは外のものとつながらないと買い物さえままならないな。じゃあこの国の人間以外か?いやいやもう分かるじゃろう。ひきこもる基準なんてないんじゃ。貴様らが勝手に他者とのつながりが小さくせざるを得ない人間をひきこもりと呼ぶのじゃ。ひきこもりとして社会問題として囚人のように勝手に扱ったのじゃ。舞はむしろそんな貴様らこそひきこもりと呼べると思うぞ。貴様らは何人の人間と親しくなれる?百人か?千人か?万か?億か?いや、それぞれに確実に限界があるのじゃ。それが人より少なくて一人や二人と親しくなれない人間もいるのじゃ。そんな人々を認められず、疎外する貴様らこそひきこもりじゃ。このひきこもりめ!!!!」
「支離滅裂ですよ。そんな理論が通るとでも?」
「それは貴様の価値観じゃ」
「一般的な意見かと」
「そうじゃろうか?」
「やけに突っかかりますね」
「じゃあ後ろの影は何じゃ?」
「え?」
男は驚いて振り返る。俺と向き合う。
向き合いながら俺はヤツの視線の先を追い、その光景に驚きのあまり思わず声を出してしまう。
「体が……」
そこにヤツは俺の形をした影ができつつあるのを見たはずだ。
「そんな、まさか……」
俺は形を得つつある口元を笑みに歪めた。
「お前ご自慢の『システム』とやらは舞の主張を正当と認めたようだな」
「わ、私は認めないぞ!!ふざけるな、間違ってない」
「だからそれは独り善がりなのじゃろ、だから現にこうなっておる」
そう言って舞は俺の影を指さす。
「ま、まさかあなたははここに来た時からこれを目論んで……」
「その通り!!舞が勝算もなくのこのこと戻ってくるわけなかろう」
不敵な笑みを浮かべる。俺だってこれで勝ったと思ったさ。
でもそのことに気付いたのは俺が最初だった。
「あれ?」
俺は手元を見つめる。
影のままの手元を。
「戻らない?」
「何じゃと?!」
そう、舞の宣言から十分な時間が経つのに俺の体は影のままで実体を持たないまま。カタガミとかいう名前の役人の体にも何も起こらない。
「どういうことじゃ!?」
「なるほど」うなだれていたヤツは勝ち誇るように笑いながら顔を上げた。「宣言が不完全だったのですね」
「なんじゃと!?」
「あなたの宣言は間違ってると言っているのですよ桜川様!!いくらかは正当だったのでしょう。だから彼の影までは出現した。しかし完全ではなかったからこのように中途半端に実体化が止まったのです。いやはや愉快ですね、やはり我々は間違っていなかったのですから」
「ちょっと待ってくれよ、よくわからない。俺はどうしたんだ?」
「舞たちの負けじゃ」
舞が唇を噛み締めながら悔しそうにつぶやく。
「は?」
「これが少年を助ける唯一の策じゃった。政府こそひきこもりであると宣言してこの男を部屋にし、少年を救出して逃げる。そんな作戦だったのだが、もう駄目じゃ。これでは逃げようがない」
そう言って俺の方を見る目は舞に似合わない、悲しみに絶望しきった黒い目だった。
「すまない。少年」
俺は言葉を失う。マジかよ。
「さてはて」男が厭な笑い方で俺と舞を舐めるように見る。「どうしてくれましょう。部屋にされかけたのですよ、私は。しかも無益な国家反逆者に。これはとても看過できる自体ではありません。しかるべき手段で裁かせていただきます」
「ちょっと待てよ、なぁ舞。なんでそんな簡単に諦めんだよ!俺の影までは出てるんだ。もう少しでこの状況だって覆せるはずじゃないのかよ!!」
「舞だって考えておる!!」堪らないかのように怒鳴り声を上げた。「だがわからぬのだ。政府は確かにひきこもる国民と向き合わなかった。しかし向き合わないままに政策は行われているのだ。これをひきこもりと言えるのか。無責任だと責められるのか……舞にはわからぬ」
「でも政府は間違っているんだろ?!」
「うむ間違っておる。だが何が間違っておるのかわからぬ」
「往生際が悪いのでは?」ヤツは端末を仕舞う。「すでに本社と連絡を取りました。もうすぐ私の仲間がこの部屋に来ます。仮にあなた方が的確な主張を思いつき、私を部屋にして逃亡したとしてもすぐに私の仲間に捕まることとなるでしょう」
「うるさい!!」
俺は怒鳴った。どうすればいいどうすればいい。考えるけど何も思いつかない。舞は思考を放棄したようにうなだれていた。くそ、舞にわからないことが俺にわかるはずもない。でも諦めきれない。あと少しなんだ。影まではできてるんだ。何かあるはずだ。何か。絶対に政府のやり方が正しいはずはないんだから。
絶対に?
「あぁ」
俺は思いついた。そして納得した。これだ。
「少年?」
舞が突然声を上げた俺を見上げる。
男も訝しげに視線を寄越す。
俺の形にならない口元が不敵に歪んだからだろう。さっきまでの舞みたいに。
「この国は間違っていない」
さっと舞の表情が曇る。男の笑みが浮かぶ。
「間違っているのは『システム』だ」
「え?」
舞が下げかけた顔を上げる。
「ひきこもる人間を部屋にするこの『システム』は、部屋として外側と内側を分ける役目も担っている。ここまではいい。だけどそのために必要なプロセスがまずい。その部屋の中でひきこもる人間を宣言するというものだ。
ならば部屋であるこの『システム』をこそひきこもりである宣言したらどうなるだろう?
ひきこもるってのは内側にあり外側との交渉を断絶する行為だけど、この『システム』は内側と外側を断絶する部屋そのものなんだ。『システム』は内側にも外側にも向きながらその一方で内側と外側を明確に区別する。区別しなければ『システム』として人間のするひきこもりの宣言を判断できないからだ。なら『システム』本体はどこにいるのか、外側か、内側か。違う。その間。境界線こそが『システム』だ。境界線にひきこもっているんだ。だからもし『システム』こそひきこもりである宣言しても少なくともそれが正当でないと否定されることはないはずだ」
政府をひきこもりだと宣言しても不完全だったのも政府が『システム』と同列に語られたからだ。政府は『システム』を使っているに過ぎず、ひきこもりに対して壁をつくるのは『システム』。だから否定すべきは『システム』の方だったのだ。
「なるほど」少し考え込んだ後、舞が納得いったというように頷く。「『システム』そのものを否定する。それは盲点じゃった。じゃが果たしてそれがうまくいくじゃろうか」
「うまくいかなくて元々だろうが、てかお前の作戦もそんなもんだったろ」
「おもしろい」いつの間にか舞の口元には俺に移ったあの笑みが浮かんでいた。「やってみろ少年!!」
「ち、ちょっと待って下さい!」呆然としていたカタガミが焦ったように声を上げる。「そんなことをして万が一にもうまくいったとしても、私の仲間がすぐにやって来てあなた方を拘束するんですから無駄です。それにそんなデタラメなことをしたら『システム』がどうなるかわかったものじゃない。『システム』はうちの技術班でも完全には扱えていない超自然的な代物なんですよ?何が起こってもおかしくないんです!」
危険だ。ほとんど怒鳴りつけるようにヤツはそう言った。
それでも俺が止まることはない。一か八かかけるならこれしかないんだ。舞を救うために。俺が救われるために。ひきこもることで色んな選択を先送りにしたかった俺は今決断する。
他の連中も俺の意思を察したらしく声を上げた。
「やめろ!!」
「行け、少年!!!」
「もうひきこもらない、俺は宣言する!!本当にひきこもっていたのはこの『システム』自体だ!!!!」
次の瞬間白い光が部屋いっぱいに満ちる。ちゃちな俺の影も掻き消えるくらい。どこかで壁の崩れるような音がする。時計が逆に回る感触。ノイズが耳の奥。鼻の奥を煙の匂いが過ぎ去る。暑くてたまらない。いや凍えそうだ。虹の橋を舞と手をつないで渡った。声がする。聞こえない。ただ微笑み合う。それだけが確かなもので。
【六章】
気がつけば俺と舞は手を繋いで部屋にいた。元の俺の部屋だった。両親が家具を片付ける前の、つい昨日まで俺が暮らしていたみたいなままの部屋だ。もちろんカタガミもいない。
「どうなったんだ?」
「わからぬ」俺と同じように周りを見回していた舞が俺の方に顔を向ける。「じゃが、少年は元にもどったようじゃな」
言われて俺は自分の体を確認した。紛うことなき十数年付き合ってきた愛すべき俺の体だ。舞の方を見ても影しかないなんてことはなく舞がこちらを見ていた。ということは。
「おい、カタガミ、だったか?いるんだろう?部屋になったのか?」
しかし声が返ってこない。ふてくされてるのか気絶でもしているのか。
「いや、」舞が俺の手を引く。「たぶんここにヤツはおらん」
「なんだって?」
「あくまで推測でしかないが。それよりも今は一先ずここから逃げるのじゃ。ヤツの仲間が追ってくる」
「あぁ、そうだった」
そう言って俺は舞と一緒に外に出る。深夜だった。国道まで無言で走り、舞が指差した車に乗り込み俺らは南へと走りだす。
「この車どうしたんだ?」
ハンドルを切りながら俺は尋ねる。
「政府の派遣した補助員の車じゃったのだが盗んでこの中で寝泊まりしてたのじゃ」
そう言って指差した後部座席にはコンビニの弁当の空が散らばっていた。片付けろよ。
「あと、そういえばどうやって男が俺のところに来たタイミングがわかったんだ?」
「盗聴器があの部屋に仕掛けられていたのは教えられたな?あれの飛ばす電波を傍受したのじゃ」
出来るのかよ。
「それよりも訊きたいことがあるのではないか?」
「あぁ」白状すると、俺はその質問を尋ねるのが怖かった。ゆっくりと質問を頭のなかで言葉にする。深夜特有のガランとしてどこまでも続きそうな大通りで、俺はアクセルを踏み込む。「あそこでヤツが部屋になっていないってのはどういうことだ?」
「うむ」舞は少し考え込んで、言葉を選ぶように語り出した。「おそらく舞たちは部屋から追い出された」
「は?」
「舞たちは存在ごと『システム』の存在する世界から追い出されたのじゃ。『システム』をひきこもりと宣言されたことから『システム』は自身を部屋としてひきこもらせる必要が出た。しかし『システム』とは境界そのものなのじゃ。内側だけを向いた部屋なんて本当は存在せず、部屋は内側を向くと同時に外側にも向いている。ならば『システム』がひきこもるには部屋の外側にあたり、自らをひきこもりと宣言する存在。つまり舞たちを追い出すしかない。ただ単に『システム』の外に追い出すのではまずい。『システム』は部屋の外側にもむいておるのじゃから」
意味がよくわからない。
「だから、どうなったんだ?ここはどこだ?」
「ここは舞たちのいた世界とは別世界じゃ。『システム』の存在せず、『政策』も存在しない世界。ただしそれ以外は全部同じ。そんな場所に舞たちは飛ばされてしまったのだと思うのじゃ」
俺は驚いて二の句がつげなかった。
別世界?そんなものが存在したのか?そんな力が『システム』にはあったのか?
「もちろん確証はないし、推論でしかない。じゃからこうして念のため、この世界にはいないはずのカタガミが呼んだ仲間から逃げておる。いないはずの政府の派遣した補助員の車でな」
「……もし仮に舞の言うとおりだとしたらどうなるんだ?」
「わからん。しかし少年の目論見は概ね成功じゃ。おかげで現に舞たちはこうして逃げている。それにここが別世界じゃろうとそうでなかろうと舞たちにはあまり関係ない」
ひきこもりじゃからの。
そう言った声はこの事態を面白がるようだった。
俺はそれを聞いてもう別世界もなにもどうでもいいような気がしてきた。なんたって隣には舞がいるんだから。
「確かに……ひきこもりだもんな」
「世界がどうなろうと関係ないのじゃ、ひきこもりはやはりすごいな」
そんな場合でもない上に、ひきこもりをやめようと必死になっていたはずの俺達は二人でひとしきり笑ってしまった。
「それよりも、悪かったな」
笑いやんでから舞は唐突に謝った。
「なにがだよ」
「演技とはいえ少年を置いて出て行ったことじゃ」
「演技だったのか」
俺マジ泣きしたんだが。
「盗聴器があるから下手に教えない方が良いのはわかっておったし、それに……」
こいつにしては珍しく歯切れが悪い。
「どうした?」
「少年はあのままではいけなかったのじゃ」
「は?」
「少年は一度部屋になって、考えたほうが良かったのじゃ。ひきこもって、誰とも関わらないということが何か。本当のひきこもりが、じゃな。昔の舞のように。そうせずにあのままただ助けても少年は舞の考えもわからなかったじゃろうしこの先も舞に依存して生きようとしたのではないかの?」
「……そうか?」
「そうじゃと言ったらそうなのじゃ」
「はぁ、ならそうなんだろうな」
とは言えよくわかってないかもしれないんだけどな。他人の考えなんてこれだと確信を持てないしそもそも正確に考えを表現するってのが不可能だ。そうだろう?だから他人を理解するなんて、結局は幻想の押し付け合いなんだ。そういう趣旨のことを俺が言うと舞は言った。
「それでも理解出来ているはず、理解されているはず。間違っているやもしれない。でもその間違いも少しずつ時間をかけて直していけるはず。そういう気持ちが信頼じゃろ」
「そうかもな」
「まるで舞達は二人だけのひきこもりじゃな」
「まだひきこもるわけだな俺らは」
俺は赤くなりながら、だけど言い切る。
反対側では舞も真っ赤になりながら声を振り絞っていた。
「じゃから、その、謝る。すまぬ。嘘とはいえ貴様を見捨てた」
「許す」
俺は即答した。
「かたじけない」
「気にするな、ところでこれからどうするんだ?」
「どうしようかの」
「決めてないのか」
「海外に出るのは決まっているのじゃがな、ここが別世界であれ、な」
「またどこかにひきこもるか?」
「だからもうすでにひきこもっているようなものじゃろう」
「それもそうだな」
「あ」
「どうした?」
「車を止めてくれ」
俺は言われたとおりに車を止める。二人で車から降りた。そこはちょうど小さな川をまたぐ橋のそばだった。
「どうしたんだ?」
「この川」舞は川を見つめていた。「舞の幼い頃よく遊んだ場所じゃ」
「四十年くらい前にか?」
「そうじゃ」まだ残っておったのだな。
そうつぶやいて、舞は黙り込んだ。橋の上の柵まで歩み寄る。俺も追いかけるように舞と同じく柵に手をかけて見下ろした。小汚いけど見てるだけで水の匂いが胸いっぱいに広がる気がする小川だった。
声を掛けるのはためらわれて、舞が過去をその瞳に映し始めるのを俺は静かに見ていた。
「舞は今ようやく気づいたかもしれない」
「何がだ?」
「外とか内とか、関係ないのじゃ」
「はぁ?」
「関係なく、変わるものもあれば変わらないものもある。変わりたいなら変わればいいし。変わりたくないなら変わらなければいい、つまりそういうことじゃ」
「……そうか」
俺にはわからなかった。だけど舞にはすでに自明のことのようだった。
そうかそうだったのか、と一人納得している。とても晴れやかな顔で。
「よくわからないな」
「少年にはわからないだろうな」
一転、舞の表情はニヤニヤと優越感に浸るものへと変わる。
「だけど俺にもひとつだけはわかるぜ」
「?」
「たぶん、俺らの関係は変わらないってことだ」
「……保護者と糞ガキか?」
「………ちげぇよ」
「冗談じゃ冗談じゃ」舞はくくくと笑う。「ありがとう」
「あぁ」
いつしか俺達は黙りこんで、川の下流に向かって二人で臨む。
俺は舞の片手を水流から目を離さずに握った。
全力でこの世界にひきこもる俺の隣で彼女はさり気なく俺の手を握り返した。
この手以外なにもいらない、と。そう思えた。
夜が明ける。
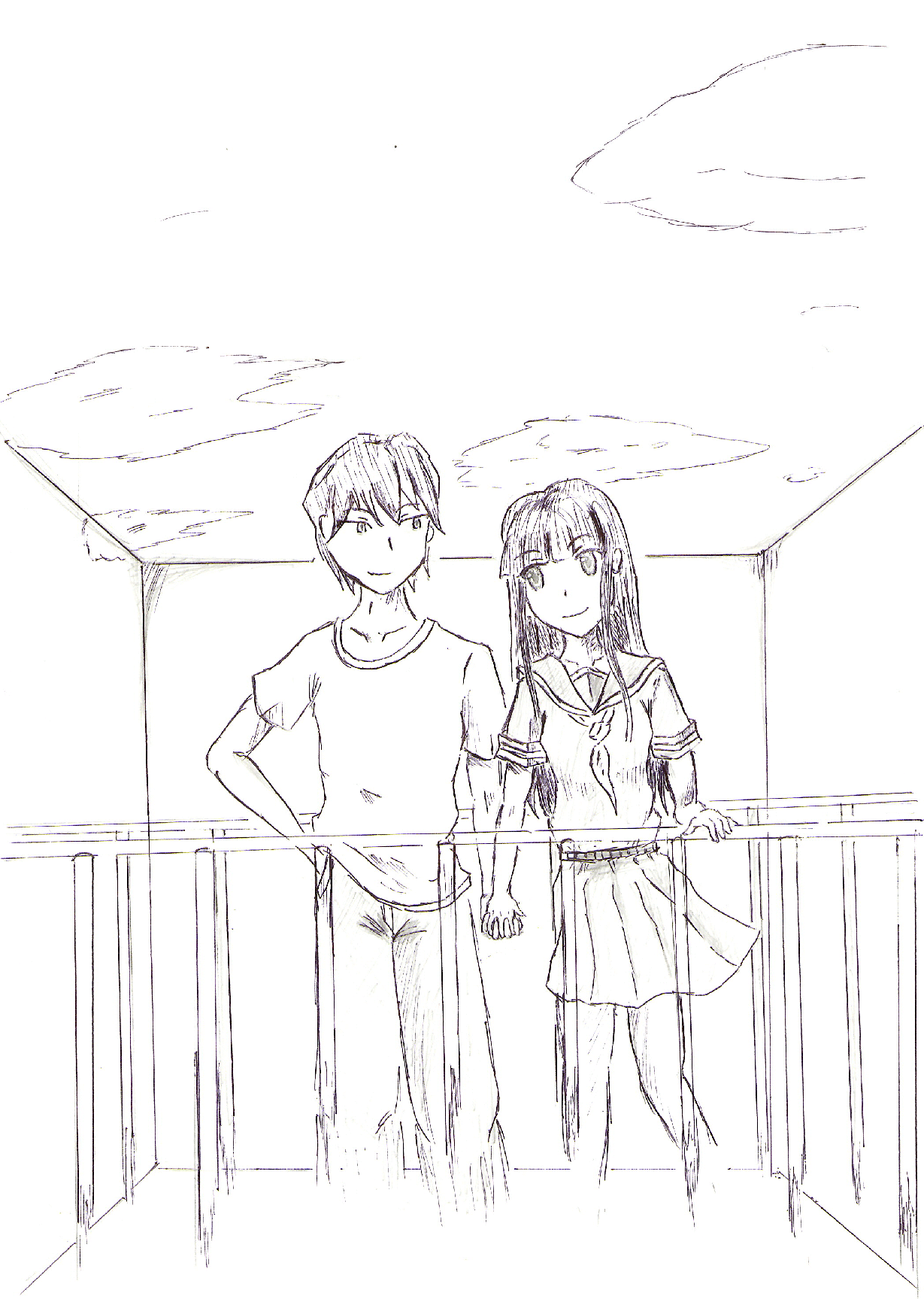
トップに戻る